コラム・ 判例・ レポート
過去の判例
2017/11/1
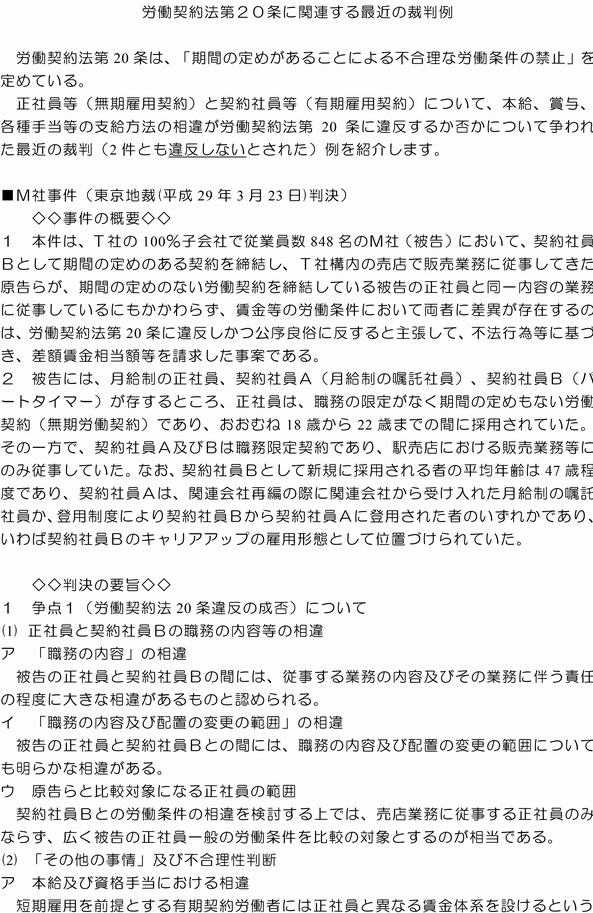
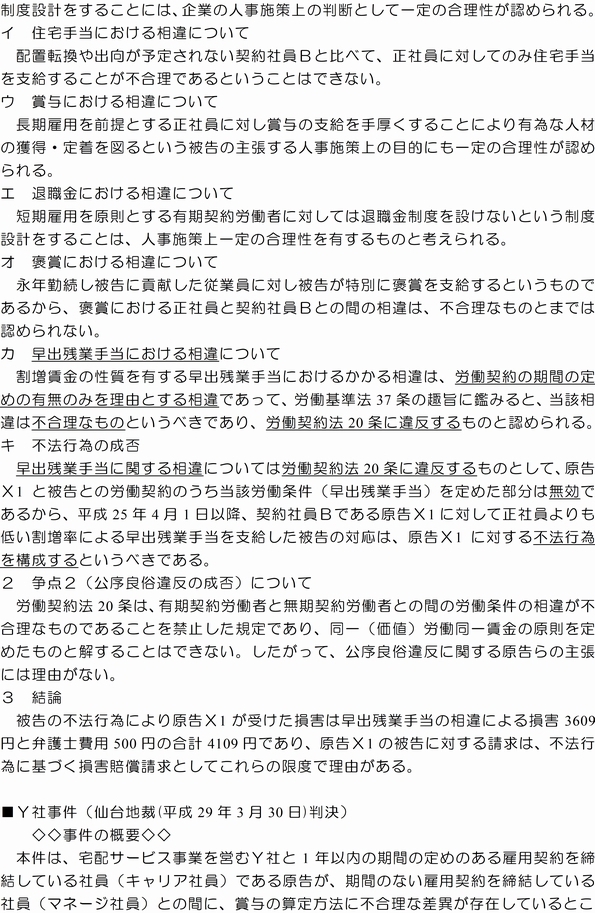
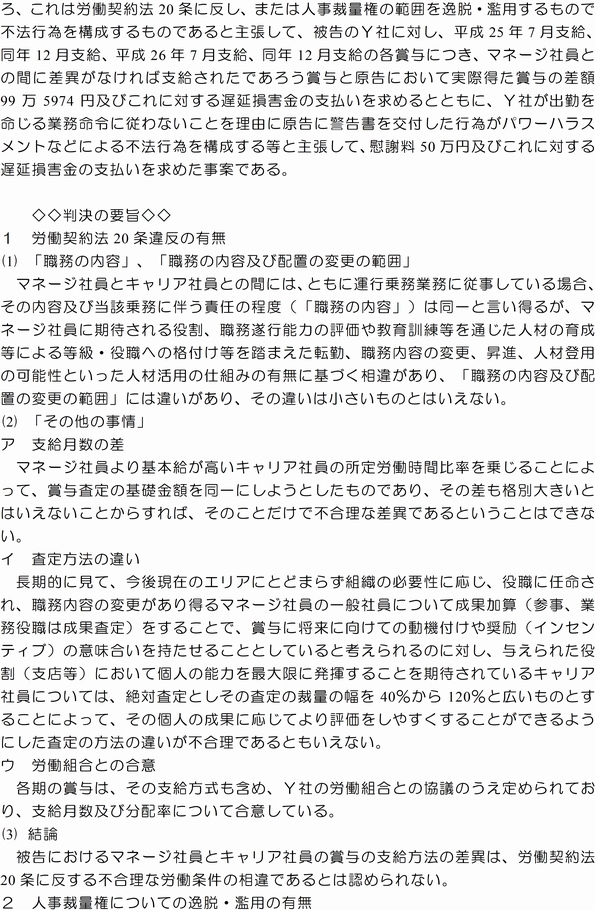
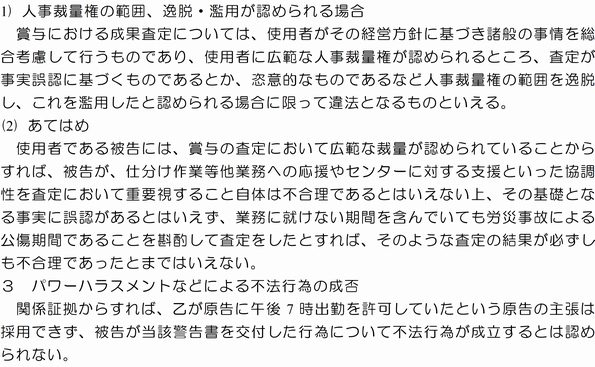
2016/12/1
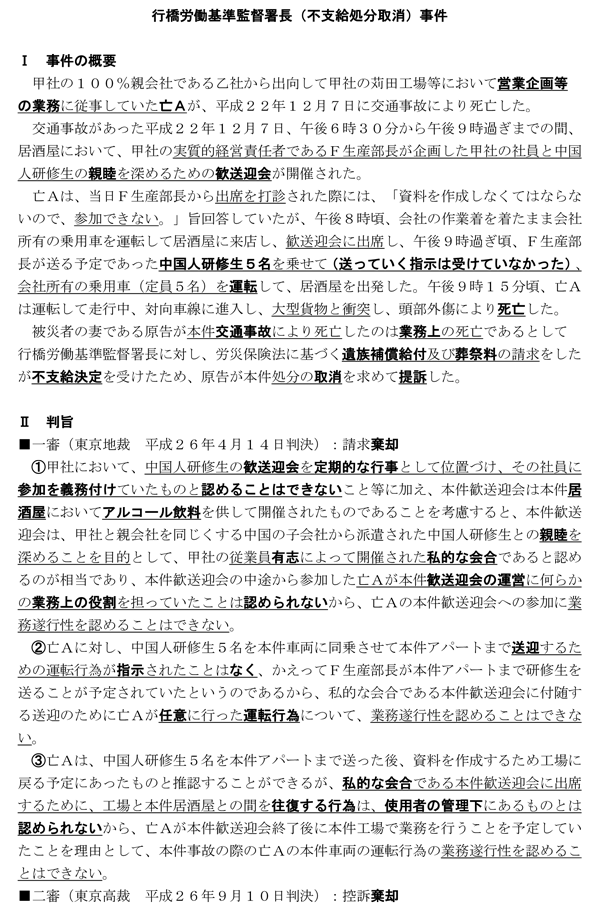
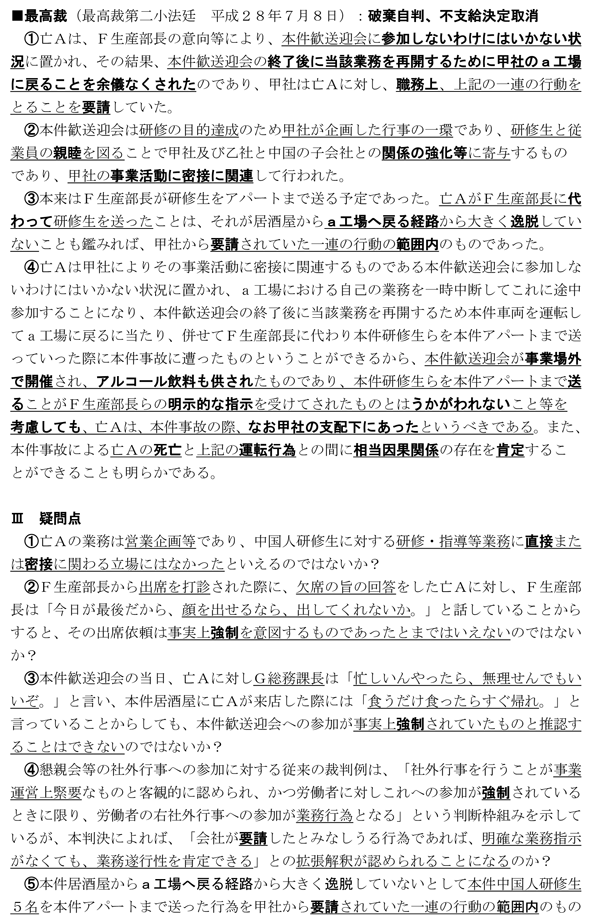
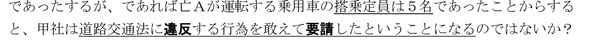
2016/9/2
労災保険の海外派遣者等特別加入
労災保険法では、次に該当する人は 海外派遣労働者等特別加入者の承認を受けることにより、保険給付を受けることができます。
①日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
そこで、 海外で勤務していた日本の会社(H社)の従業員であるAが急性心筋梗塞で死亡した事案にかかる労災保険の保険給付の適用に関する最近の裁判例を紹介します。
【事案の概要】
(1) 亡Aは、平成元年4月1日訴外H社に入社(横浜営業所で営業担当)した。
(2) 平成14年10月10日から
香港事務所で勤務し、その間に香港、上海、東京間を頻繁に往来していた。また、
平成14年10月10日から平成15年12月2日まで海外派遣者として労災保険に特別加入していた。
(3) 平成18年5月
丙社(上海)首席代表として赴任、8月には家族も上海へ転居した。
(4) 平成21年7月から
上海現地法人乙社の設立に関与し、同22年4月
乙社総経理に就任した。なお、
丙社首席代表とは兼任であった。
(5) 平成22年7月23日Aは急性心筋梗塞を発症し、上海で死亡した。
(6) 平成24年5月24日亡Aの妻(原告)がAの死亡は業務上のものであるとして労災保険法にもとづく遺族補償給付等を請求したところ、同年10月18日所轄労働基準監督署長は、
亡Aを海外派遣者であると判断するとともに、
特別加入者としての承認を受けていなかった以上、労災保険法に定める保険給付は受けられないとする
不支給処分の決定をした。
(7)
審査請求、
再審査請求を経て原告は、国を相手に
訴えを提起し不支給決定の取消を求めた。
【一審の判断及び判旨】
亡Aは、
日本国内の事業主(H社)から、海外にある中小規模の事業(乙社及び丙社)に事業主等(総経理及び首席代表)として派遣されていた者と認定し、よって、
海外派遣者等特別加入者としての承認を受けていなかった以上、労災保険の適用はなく、遺族補償給付等の
不支給は違法とはいえないとして、被告(国)の判断を支持し、原告の請求を
棄却した。
【二審の判断及び判旨】
海外事業場(乙社及び丙社)は実体(独立性)がなく、亡Aは日本の事業場(H社)に属し、ことごとくその事業場から指揮命令を受けて業務を行っていたとして、亡Aを
海外出張者と認定するとともに、一審判決を取消し、控訴を
認容した。
【私見】
私は、上智大学名誉教授山口浩一郎氏の下記見解を全面的に支持するとともに、二審の判断には明らかな法令違反があると考えます。
「一審判決は、海外事業場たる
乙社及び丙社の法的地位ないし機能における独立性は高いと認定し、さらにその
組織面においても
活動面においても
独立した活動単位としての実質を有しているとの判断にもとづいて亡Aを海外派遣者として認定したのであるが、私は、この方が事実に即した妥当な判断だと思う。海外事業場の
独立性を否定する本(二審)判決の判断は、著しく経験則に反しており、認定判断として問題であるだけでなく、このような
恣意的・意図的な認定判断では
海外派遣者は事実上なくなってしまい、特別加入制度は崩壊してしまう心配がある。(季刊「ろうさい」2016年夏号VOL.30 14頁)」
本事案に対しては、原処分庁たる
所轄労働基準監督署長さらに不服申立審査機関たる
労働保険審査官及び
労働保険審査会において、
確固たる信念の下、いずれも一貫して亡Aを
海外派遣者であると判断し当該処分を行ってきた。そしてその判断は
一審判決においても
支持されてきた。にもかかわらず、二審においてその判断が否定され、処分を取消すべく判決がなされたからといって、被控訴人(国)がその判断に何らの異議を唱えないで判決を確定させたことに対しては、行政に対する不信感を禁じ得ない。さらには、自分たちの判断に確固たる信念があるのであれば、原(二審)判決に
は明らかな法令違反があるとして、
上告受理申立をすべきであり、それをしないで二審判決を確定させたことは紛れもなく行政における
職務怠慢であるといわざるを得ない。
ところで元はといえば、日本国内の事業主(H社)が適切な労務管理の下、亡Aに対して海外派遣労働者等特別加入者としての承認を受けてさえ(
実際、亡Aが香港事務所で勤務していた平成14年10月10日から平成15年12月2日までは海外派遣者として労災保険に特別加入していた)いれば、本事案のような訴訟が提起されることはなかったといえる。その意味で、
訴外H社には、債務不履行ないしは不法行為に基づく賠償責任が求められる余地はあると思われる。
なお、原処分庁の所轄労働基準監督署長が当初から亡Aを海外派遣者ではなく海外出張者であるとの判断の下に支給・不支給の処分を決定する場合には、
当該急性心筋梗塞と業務との間の相当因果関係の存否がその判断基準となり、訴訟における争点も本事案とはまったく違ったものとなってくる。
文責:ニチハク労働事務所 日髙博幸
2016/4/11
最近の注目の労働(損害賠償請求)事件
今回ご紹介する事件の企業は、いずれも 大企業あるいは 国又は 地方公共団体ですので、 損害賠償額が企業側にもたらすダメージはたいしたことではないでしょうが、これが 中小零細企業であれば、 倒産の可能性が危惧されるといっても決して過言ではありません。
“ 事が起きてから”では、“ 手遅れ”なのです。御社の リスク管理に不備はありませんか?
ニチハクグループがご提供させていただくいろいろな情報を企業経営に是非活用してみて下さい。
1 ワタミフードサービス事件
森美菜さん(当時26歳)は、2008年4月に居酒屋「和民」に入社し、同月中旬から神奈川県横須賀市内の店舗に配属されました。連日、午前4~6時まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課され、5月中旬までの1か月間で時間外労働は「過労死ライン(月80または100時間)」を大幅に上回る月141時間に上りました。同月中旬に適応障害を発症し、入社からわずか2ヶ月後の6月12日、自宅近くのマンションから飛び降りて 自殺したのです。
2012年2月、神奈川労働局は、 残業が月に 100時間を超えるなど過労が原因だったとして、女性の死亡を 労災と認定しました。
一方、森美菜さんが自殺したのは 過重労働が原因だとして、両親が運営会社の「ワタミ」や創業者で当時社長だった渡辺美樹参院議員などに 約1億5300万円の損害賠償を求めて2013年12月に提訴し、係争していましたが、2015年12月8日、東京地裁(吉田徹裁判長)で、会社側が、自殺は過労が原因だと認めて遺族に謝罪するとともに、 1億3300万円余りの損害賠償を支払うことで「 和解」が成立しました。
なお、和解条項では、自殺は過重労働を強いたことが原因だったとワタミ側が認め、渡辺氏が最も重大な賠償責任を負うと明記された他、会社側が、平成20年以降に入社した社員に未払いの賃金の分などとして一律2万円余りを支払うとともに、残業時間の削減に努めることとし、また、ワタミが労働基準監督署から是正勧告を受けた場合、全従業員に周知するなどの過重労働再発防止策が盛り込まれています。
2 岐阜県庁事件
岐阜県職員の30代の男性は、2012年4月から県施設の建て替えに関する業務などを担当していましたが、秋頃から体調不良を訴え、2013年1月に自宅で 自殺しました。
男性が自殺したのは職場の上司から厳しい言葉で叱責されるといった パワーハラスメントや、 残業が4か月連続で 月100時間を超えるなどの長時間労働が原因だとして、自殺した職員の妻と娘が県に1億600万円余りの損害賠償を求めていました。
2014年9月、上司による不適切な発言( パワーハラスメント)と長時間労働が自殺との因果関係において、一般企業の労災にあたる 公務災害として認められました。
裁判では遺族側と県側が協議を重ねた結果、2016年1月8日岐阜地裁(武藤真紀子裁判長)で、県が遺族に和解金や未払いの時間外勤務手当として 9600万円を支払うことで「 和解」が成立しました。しかし、和解条項の中に謝罪の言葉は盛り込まれなかったようです。
3 イビデン事件
電子部品製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)に勤務していた30代(当時)の男性は、2013年4月から岐阜県内の工場で設計を担当していたが、上司から「何でできんのや」「バカヤロー」などと暴言を浴びせられたり、他の社員がいる前で約30分間立たされたまま叱責されたりした。男性は同年10月に滋賀県内の自動車内で 自殺した。
自殺前の4~10月の 残業時間は 月約68~141時間だった。大垣労働基準監督署は2015年1月、指導の範囲を逸脱した上司の叱責と長時間労働が原因で、男性が適応障害を発症したなどとして 労災を認定しました。
遺族は、男性社員が自殺したのは、上司の パワーハラスメントや 長時間労働が原因だとして、同社と上司に対して計 約1億550万円の損害賠償を求めて2016年1月に提訴しました。
2016年3月10日、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)で第1回口頭弁論が開かれました。当初は請求棄却を求めていましたが、同社は請求を全面的に認める「 認諾」をし、訴訟は終結しました。
2015/8/5
労災保険の中小事業主等特別加入
労災保険(業務災害と通勤災害)で給付が受けられる者は、原則として労働者に限られます。従って、労働者ではない者(例えば、個人事業主及び家族従業員や法人の理事及び取締役等)は、給付を受けることはできません。
しかしながら、中小企業の事業主等や取締役等(これらの者を、中小事業主等といいます。)は、労働者と同様の業務に従事していることが一般的であるにもかかわらず、労災保険の補償が受けられないということは、現実的ではありません。そこで、労災保険法は、従業員規模が300人以下(製造業等)の中小事業主等については、特別加入という制度により、労働者と同様の労災保険の給付が受けられる途を設けています。
ただし、特別加入をするには、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することが必要になります。
中小事業主等においては、明らかに労働者であると判断できる者以外の者に対しては、特別加入の申請をしておくことがリスク管理の上で賢明な対策であると思われます。
ところで、 国・船橋労基署長(マルカキカイ)事件(東京地裁 平成23.5.19判決)では、出張中、突然目の痛みを訴えるなどして病院に救急車で搬送されたが、同日、病院において橋出血により死亡した 執行役員Aについて、船橋労働基準監督署長は、労基法9条に該当する労働者として認められないとして、遺族補償給付を不支給としました。また、 大阪中央労基署長(おかざき)事件(大阪地裁 平成15.10.29判決)では、主張中の宿泊先のホテルのベットの上で、急性循環不全のため死亡した 専務取締役Bについて、大阪中央労働基準監督署長は、労基法9条に該当する労働者として認められないとして、遺族補償給付を不支給としました。いずれの事件も労災保険法上の不服申し立て手続を経た後に、当該処分の取消しを求めて提訴された行政訴訟で、 執行役員A及び 専務取締役Bは 労働者であると認定され、当該不支給処分が取り消されました。
しかしながら、上記2つの事件は、例外的な事案といわざるを得ません。また、労働者に該当しないことを理由とする不支給処分が取り消されたからといって、当然に当該遺族補償給付の支給が決定されるとは限りません。当該死亡の原因が本当に業務に起因するものなのかどうかを検討した上で、相当因果関係が認められて初めて支給決定がなされることになりますが、幸い(?)にも2つの事件とも業務起因性が認められ、遺族補償給付が支給されました。
なお、マルカキカイ(株)は、上場企業で中小事業主には該当しませんので、取締役や執行役員が仮に特別加入したいと思っても、加入することはできませんが、(株)おかざきは、中小事業主ですので、取締役等全員が特別加入を申請していれば、前述のような不服申し立て手続や訴訟の提起は必要がなかったのです。また、(株)おかざき及び代表取締役Cは、専務取締役Bの遺族から民事訴訟による損害賠償を請求され、約2,800万円の支払いを命じられました。
文責:ニチハク労働事務所 日髙博幸
打切補償と解雇制限の解除
労基法は、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」(労基法第19条1項本文)という解雇制限の規定を定めているが、この解雇制限は「第81条の規定によって打切補償を支払う場合」、すなわち労基法上の療養補償(労基法75条)を受ける労働者に対して打切補償を行う場合には、解除されると定められている(労基法19条1項但書前段)。
では、労基法上の療養補償ではなく、労災保険法上の療養補償給付を受ける労働者に対し、打切補償を支払った場合にも、果たして解雇制限が解除されるのか、どうかが争われた事件が S大学事件(東京地裁 平24.9.28判決、東京高裁 平25.7.10判決、最高裁二小 平27.6.8判決)である。
東京地裁判決は、労災保険法上の療養補償給付を受ける労働者に対し打切補償を支払っても労基法19条の解雇制限を解除することはできず、当該解雇は 無効である旨判示した。
東京高裁判決は、要旨次のとおり判断し、本件解雇は労基法19条1項に違反し 無効であるとして、第一審の判決を相当とする旨判示した。
「労基法81条(打切補償)は、同法75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合において、打切補償を行うことができる旨を定めており、労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者については何ら触れていないこと等からすると、労基法の文言上、労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者が労基法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当するものと解することは困難である。したがって、本件解雇は、同法19条1項但し書所定の場合に該当するものとはいえず、同項に違反し無効であるというべきである。」
最高裁判決は、要旨次のとおり判断し、原判決を 破棄するとともに本件解雇の有効性に関する労契法16条該当性の有無等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に 差し戻した。
「労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労基法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である(最高裁三小 昭52.10.25判決)。労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労基法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項但し書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」
文責:ニチハク労働事務所 日髙博幸
